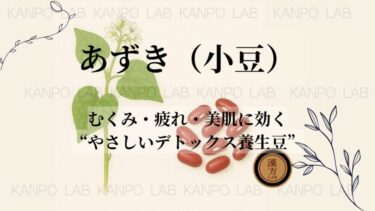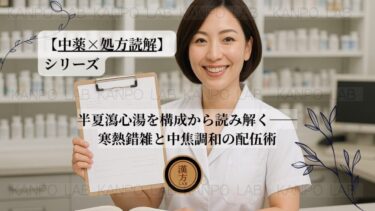目次
心配性・くよくよする人は「脾虚体質」に注意!|思考と消化の関係とは?
「小さなことが気になって仕方ない」「いつまでも同じことを考えてしまう」
そんな心配性・くよくよ思考のクセがある方は、実は脾(ひ)=消化器系の弱りと関係しているかもしれません。
中医学(東洋医学)では、“脾は思を主る(しはおもいをつかさどる)”とされ、思い悩む感情は脾に影響し、また脾の虚弱がその感情を助長すると考えられています。
この記事では、「思考と消化の関係」を中医学的に解説し、脾虚体質に対応した漢方・薬膳・生活改善のヒントをお届けします。
なぜ「脾虚体質」は心配性になりやすいのか?
脾は、食べ物から「気(エネルギー)」や「血(栄養)」を作り出す消化器官にあたります。
同時に、過度な思慮=くよくよ思考は、脾の働きを抑えてしまうとされ、以下のような“負のループ”が生まれます:
- 心配しすぎる → 胃腸が弱る
- 胃腸が弱る → 気血が作れない → 不安が増す
このように、脾虚体質の人は「思いすぎによる消化不良・不安感・疲れやすさ」といった不調が複合的に現れます。
脾虚体質セルフチェック
- 思い悩みやすく、気持ちの切り替えが苦手
- 胃腸が弱く、食後に眠くなる・もたれる
- 軟便・下痢をしやすい
- 顔色が黄色っぽく、疲れやすい
- 眠っても疲れが取れにくい
- めまい・ふらつき・貧血傾向
上記のような傾向が強い方は「脾虚+心血不足」の体質かもしれません。
脾虚タイプに使われる漢方処方
① 加味帰脾湯(かみきひとう)
疲労・くよくよ・食欲不振・不眠に。心と脾を同時に補う定番処方。
② 補中益気湯(ほちゅうえっきとう)
脾気虚+気の下陥による疲労・食欲低下・やる気のなさに。
③ 六君子湯(りっくんしとう)
食が細く、消化力が弱いタイプ。胃もたれ・食後の眠気にも対応。
④ 炙甘草湯(しゃかんぞうとう)
心悸・疲れ・舌の乾燥など、虚弱型の心脾ケアに用いられます。
脾を元気にする薬膳素材
消化機能を助ける食材
- 山芋:胃腸を補い、疲労回復にも
- なつめ:気血を補い、精神安定に
- かぼちゃ・じゃがいも:脾を補い、甘味で安心感を与える
- 大麦・はとむぎ:湿気を取り、脾の動きを整える
おすすめの食事
- 山芋と鶏ささみのやさしいスープ
- なつめ入り雑穀粥
- かぼちゃのやわらか煮+すりごま
生活でできるケア習慣
1. 思考の“オン・オフ”を意識する
- あえて「何も考えない」時間をつくる
- 書く・話すことで頭の中を整理する
2. リズムを整える
- 決まった時間に食事・睡眠
- 「脾」は乱れに弱いため、一定の生活が重要
3. ゆるく動かす
- 軽いストレッチ・散歩で気を巡らせる
- 湿気の多い日は体を冷やさないよう注意
まとめ|「考えすぎる」は、体質から変えられる
「心配性」「くよくよする性格」――そう思い込んでいたことが、実は脾虚という体のアンバランスから来ていたとしたらどうでしょうか?
中医学では、思考や感情も五臓六腑のバランスの一部。
だからこそ、体から心を整えるというアプローチが可能なのです。
考えすぎて疲れたときは、自分を責めず、まずは胃腸をいたわることから始めてみましょう。