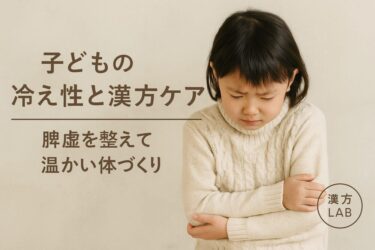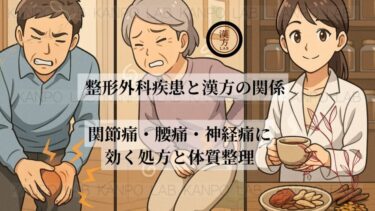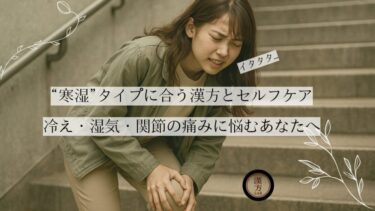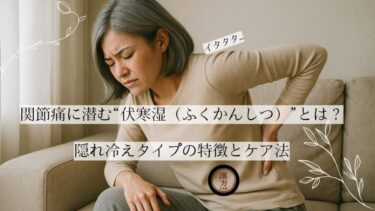関節痛は“隠れ冷え”かもしれない|伏寒湿(ふくかんしつ)体質の特徴とケア法
関節が痛む、だるい、こわばる──でも「冷えてないのに」「検査では異常なし」と言われて困っていませんか?
中医学では、こうした表面化しない冷えを「伏寒(ふくかん)」と呼び、体内に潜む“隠れ寒”が不調の根本にあると考えます。
伏寒湿(ふくかんしつ)とは?
伏寒とは、外から入った寒邪(かんじゃ:冷え)が十分に発散されず、体内に残ってしまう状態です。
特に湿気と結びつくと「寒湿(かんしつ)」となり、それがさらに深層にこもると「伏寒湿」となります。
特徴としては以下のような傾向があります:
- 冷えをあまり自覚していないのに、関節や腰の痛みが続く
- 痛みの部位が移動する、あるいは曖昧でつかみどころがない
- 舌の苔が白く、湿っている/脈が沈んで弱い
- お風呂やカイロで温めると症状が楽になる
一見“冷えていないように見える”この状態を「伏寒」と見抜くには、中医学的な視点が欠かせません。
西洋医学との違い──“検査で異常がない”の理由
西洋医学では、関節の腫れや炎症、血液所見など「目に見える異常」が重視されます。
一方、中医学では「まだ病気になりきっていない状態=未病」をとらえ、**証(しょう)として体質傾向を見る**のが特徴です。
伏寒湿は、まさにこの「未病」の典型であり、冷え・湿気・巡りの滞りが絡む複雑な証です。
伏寒湿タイプに合う漢方処方
伏寒湿に対応する処方は、単なる「温める」だけでなく、体内にこもった寒と湿を“抜く”ことが重要です。
- 苓姜朮甘湯(りょうきょうじゅつかんとう)
【効能】温陽・化湿・祛寒。関節痛、腰痛、寒冷に悪化するタイプに。
👉 方剤辞典で詳しく見る(※現在構築中です)
- 桂枝加苓朮附湯(けいしかしょうじゅつぶとう)
【効能】温経散寒・除湿止痛。高齢者や慢性痛に用いられます。
👉方剤辞典で詳しく見る(※現在構築中です)
セルフケアのポイント|温めて“巡らせる”
■ 入浴・温活
シャワーで済ませず、毎日お風呂に浸かることが伏寒湿のケアには必須です。以下もおすすめです:
- よもぎ・生姜・みかんの皮などの薬湯
- 足湯+腹巻+首元を冷やさない衣類
■ 薬膳
- 温性食品:ねぎ、にんにく、シナモン、羊肉
- 湿を取る:はとむぎ、小豆、冬瓜、山椒
👉 冬におすすめの薬膳素材はこちら(※準備中)
■ ツボ刺激
- 命門(めいもん):おへその真裏、腰の中心部に位置し、腎陽を温める要穴
- 陽池(ようち):手首の背面中央に位置し、寒湿によるこわばりに
- 足三里(あしさんり):胃腸虚弱・冷え・だるさに幅広く対応
👉 経絡一覧はこちら(※現在構築中)
伏寒湿タイプの人に多い生活習慣
- 冷房が強い場所に長時間いる
- 冷たい飲食が多い(水・アイス・生野菜)
- 汗をかいたまま放置する習慣がある
- 運動不足、長時間同じ姿勢
これらは伏寒湿を悪化させる要因となるため、生活から見直すことも大切です。
まとめ
表に出ない冷え=「伏寒湿」は、気づきにくく、長引く関節痛の原因にもなり得ます。
中医学の視点で体の内側を見立て、証に合った温活・食養生・ツボ刺激を取り入れていきましょう。
▶ ご自身の体質傾向をチェックしてみる: