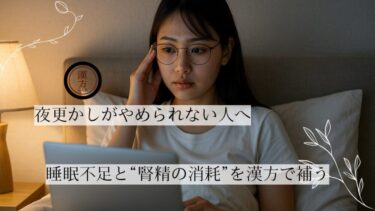夜泣きは体質のサイン?漢方で穏やかな眠りをサポート
はじめに
「夜になると泣き止まない」「突然目を覚まして泣き続ける」—— 小さなお子さんの夜泣きに困っていませんか?
中医学では、夜泣きは単なる成長の一過性のものではなく、体質や心身のバランスの乱れによって起こると考えられています。
この記事では、夜泣きの原因と、体質に合わせた漢方ケアをご紹介します。
中医学で考える夜泣きの原因
夜泣きは、中医学では「驚悸(きょうき)」や「驚風(きょうふう)」と呼ばれ、次のような体質的要因が関係するとされています。
1. 心脾両虚(しんぴりょうきょ)
- 心(しん)の安定と脾(ひ)の気が不足し、不安感が強くなる
- 寝付きが悪く、浅い眠りで夜中に何度も起きる
2. 肝鬱化火(かんうつかか)
- 情緒が不安定で、怒りっぽく、イライラしやすい
- 夜になると熱を帯びたように興奮し、目を覚ます
3. 驚風・痰熱(たんねつ)
- 体内に痰や熱がこもり、眠りを妨げる
- 体が熱く、汗をかきやすい
体質別・漢方ケアの提案
心脾両虚タイプ
- 帰脾湯(きひとう) – 心を安定させ、脾を補う
- 甘麦大棗湯(かんばくたいそうとう) – 不安感が強く、泣き止まない場合に
肝鬱化火タイプ
- 竜胆瀉肝湯(りゅうたんしゃかんとう) – 肝の熱を冷まし、情緒を整える
- 柴胡加竜骨牡蛎湯(さいこかりゅうこつぼれいとう) – イライラ、興奮を鎮める
痰熱タイプ
- 温胆湯(うんたんとう) – 胃腸の痰熱を取り除き、眠りを深くする
- 黄連解毒湯(おうれんげどくとう) – 熱が強い場合の体質改善に
家庭でできるケアのポイント
- 寝る前は、明かりを暗くし、静かな環境を整える
- 日中にしっかり体を動かし、適度な疲れを促す
- 冷たいもの、甘いものを控え、消化にやさしい食事を
- 寝る前のスキンシップで安心感を与える
まとめ
夜泣きは体質のサインかもしれません。
中医学では、体のバランスを整えることで、穏やかな眠りを導くと考えます。
体質に合った漢方ケアと、日々の生活習慣を見直しながら、お子さまの心と体を優しく支えていきましょう。