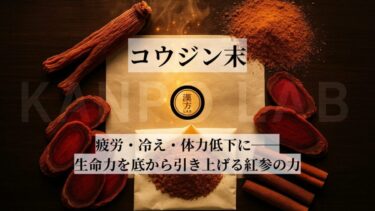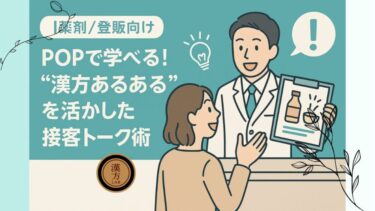咳・喘息・息苦しさを中医学で読み解く
─ 中医内科学に基づく「肺」の見方と治療の全体像 ─
① 導入:現代医療では見落とされがちな“咳・喘息”の背景とは
「咳が何週間も止まらない。でも、レントゲンも血液検査も異常なし」
「子どもが喘息と診断されたが、薬をやめるとすぐに再発する」
「夜になると息苦しくなるが、原因が分からない」
—— こうした声は、実際の医療現場でも少なくありません。
西洋医学では“症状”や“臓器”に対する検査・治療が主となりますが、それでは掬いきれない不調が確かに存在します。
そこで注目されるのが、中医学の視点です。
中医学では「咳」や「喘息」は単なる症状ではなく、「肺気の失調」や「気血の運行の乱れ」として全身のバランスから診ていきます。
本記事では、咳・喘・呼吸困難といった呼吸器症状を中医内科学の立場から解説し、病因病機・証型・治療法までを体系的に整理します。
② 呼吸器系疾患とは|中医内科学における定義と分類
中医内科学では、咳や喘息などの呼吸器症状を主とする病証を以下のように分類しています。
■ 咳嗽(がいそう)
咳を主症とする病証。肺気が逆流し、外へと咳となって現れます。
「咳」はあくまで“症状”ではなく、“病名”として取り扱われます。
■ 哮病(こうびょう)
痰の壅盛により喉中に哮鳴音(ゼーゼー)を生じる発作性疾患。
発作と寛解を繰り返す慢性経過が特徴です。
■ 喘証(ぜんしょう)
呼吸困難、特に吸気困難を主症とする疾患。
「上気して息が続かない」といった状態を指し、実証・虚証ともに存在します。
③ 病因・病機|なぜ「肺」は病みやすいのか?
中医学において「肺」は「嬌臓(きょうぞう)」と称されます。
これは、肺が繊細で外邪の影響を受けやすく、寒熱・乾湿・風などに反応しやすい性質を持つことを意味します。
主な病因
| 病因 | 解説 |
|---|---|
| 風寒・風熱(外感邪気) | 肺の宣発・粛降が障害され咳・喘が発生する |
| 燥邪 | 肺陰を損傷し、空咳・痰少・喉の乾燥が出現 |
| 飲食不節 | 痰湿が生じ、肺に上壅して呼吸困難を招く |
| 情志失調 | 肝気が肺を犯し、咳・哮を誘発する |
| 労倦・久病 | 肺気虚・腎虚を招き、慢性の喘・咳を生む |
肺の生理と関係する病機
- 肺は「気の主」「呼吸を主る」:咳嗽は肺気の上逆、喘証は肺気の閉塞
- 肺は「宣発・粛降」を司る:外邪によりこれが阻まれると咳・痰・喘が発生
- 肺は「水の上源」:腎・脾と連携して津液を調整。腎虚による水液不化も原因に
④ 証型分類|どのような“咳・喘”かで診立てが変わる
中医学では「咳」や「喘」は、それぞれ異なる“証”として分類されます。
症状の性質、痰の状態、寒熱の有無、発作のタイミングなどをもとに、適切な証型を見立て、治療方針を定めます。
1. 風寒咳嗽(ふうかんがいそう)
- 主症:悪寒、発熱、咳嗽、白く薄い痰、鼻づまり、無汗
- 病機:風寒の外邪が肺を束縛し、肺の宣発機能が失調
- 舌脈:舌苔白、脈浮緊
2. 風熱咳嗽(ふうねつがいそう)
- 主症:咳嗽、粘稠の黄痰、発熱、喉の痛み、口渇
- 病機:風熱邪が肺に侵入し、肺熱によって咳が誘発される
- 舌脈:舌尖紅、舌苔薄黄、脈浮数
3. 燥熱咳嗽(そうねつがいそう)
- 主症:乾いた咳、痰が少なく粘い、鼻や口の乾燥、微熱
- 病機:燥邪が肺を傷つけ、肺陰を損傷し潤いを失う
- 舌脈:舌乾紅、苔少、脈細数
4. 痰湿阻肺(たんしつそはい)
- 主症:痰が多く粘り、咳が重い、胸悶、倦怠感
- 病機:脾虚により痰湿が生じ、肺の粛降が阻害される
- 舌脈:舌苔白膩、脈滑
5. 肺陰虚咳嗽(はいいんきょがいそう)
- 主症:空咳、痰が少ない、口乾、のどの渇き、頬紅、寝汗
- 病機:久病や燥熱によって肺陰が損傷され、陰虚内熱となる
- 舌脈:舌紅少苔、脈細数
6. 腎虚喘証(じんきょぜんしょう)
- 主症:息切れ、呼吸困難、腰膝のだるさ、疲労感、夜間の悪化
- 病機:腎気虚により納気不固となり、肺気が下に降りなくなる
- 舌脈:舌淡、脈沈細
⑤ 治法と方剤|証型ごとの治療戦略
中医学では、「証」に基づいて治法を定め、それに応じた方剤(漢方処方)を選択します。
ここでは、呼吸器疾患における代表的な証型に対応する治法と代表方剤をご紹介します。
1. 風寒咳嗽
- 治法:疏風散寒、宣肺止咳
- 代表方剤:三拗湯、杏蘇散、荊防敗毒散
2. 風熱咳嗽
- 治法:疏風清熱、宣肺止咳
- 代表方剤:桑菊飲、銀翹散、桔梗石膏湯
3. 燥熱咳嗽
- 治法:養陰清肺、潤燥止咳
- 代表方剤:清燥救肺湯、沙参麦門冬湯
4. 痰湿阻肺
- 治法:燥湿化痰、宣肺止咳
- 代表方剤:二陳湯、平胃散、参蘇飲
5. 肺陰虚咳嗽
- 治法:養陰潤肺、清熱止咳
- 代表方剤:百合固金湯、沙参麦門冬湯、養陰清肺湯
6. 腎虚喘証
- 治法:補腎納気、平喘
- 代表方剤:金匱腎気丸、参蛤散、右帰丸(虚寒)、左帰丸(陰虚)
⑥ 鑑別|似た症状をどう見分ける?
咳や喘鳴、呼吸困難といった症状は、さまざまな疾患や証で共通して見られます。
中医学では、これらを弁証によって見分け、個々に応じた治療戦略を立てることが重要とされます。
■ 咳嗽 vs 喘証
- 咳嗽:主に肺気の上逆による「咳」が主症。発声として咳が強い。
- 喘証:呼吸困難が主であり、吸気障害・胸部緊迫感が中心。
■ 哮病 vs 喘証
- 哮病:発作性で、痰が壅塞し喉中に哮鳴音(ゼーゼー)を伴う。反復性。
- 喘証:慢性・実虚いずれにも出現。哮鳴が目立たず、気の昇降障害が中心。
■ 中医学的「咳」と西洋医学の「咳」
- 西洋医学では「咳=症状」であり、原因疾患の結果として扱われる。
- 中医学では「咳嗽」は独立した病名であり、
外感・内傷・臓腑機能の失調を原因とする“全身の失調”ととらえる。
■ 他症状との鑑別(重要ポイント)
- 痰多で咳き込む:痰湿阻肺 or 痰熱壅肺
- 空咳で痰少:肺陰虚 or 燥邪犯肺
- 急性発作で息苦しい:哮病(実証)
- 慢性疲労や高齢で息切れ:腎不納気による喘証(虚証)
⑦ 現代疾患との比較|喘息・COPD・気管支炎との対応関係
中医学と西洋医学では、疾患の捉え方や治療の着眼点に大きな違いがあります。
ここでは、代表的な現代医学の呼吸器疾患を中医学的にどう見立てるかを比較してみましょう。
■ 気管支喘息(Bronchial Asthma)
- 西洋医学:アレルギー性炎症による気道過敏性の亢進と可逆的狭窄
- 中医学対応:哮病・喘証に該当
- 主な証型:痰熱壅肺、痰湿阻肺、腎虚不納気
■ 慢性閉塞性肺疾患(COPD)
- 西洋医学:慢性気管支炎・肺気腫による呼吸機能の低下
- 中医学対応:喘証、肺脾気虚、腎不納気
- 主な証型:肺気虚・腎陽虚・痰湿阻肺
■ 急性気管支炎
- 西洋医学:ウイルスや細菌感染による気道の一時的炎症
- 中医学対応:風寒咳嗽・風熱咳嗽
- 主な証型:風寒犯肺、風熱犯肺
■ 中医学ならではの視点
- 同じ「喘息」でも、体質や季節、発症パターンにより異なる証に分けて治療する
- 中医学は「症状」だけでなく「病因」「体質(証)」を重視
- 呼吸器に表れる症状を通して、腎・脾・肝など他臓腑の状態も同時に評価する
⑧ セルフケア|薬膳・ツボ・養生で肺を守る
中医学では「治未病(ちみびょう)」、すなわち未然に病を防ぐという考え方を重視します。
咳や喘息などの呼吸器トラブルを防ぐためには、日常生活でのセルフケアも重要な位置づけとなります。
■ 養生の基本:肺は“潤い”と“清潔”を好む
- 乾燥を避ける(特に秋〜冬):加湿器、白湯、潤い食材の摂取
- 呼吸を深く整える習慣:深呼吸、気功、呼吸瞑想など
- 冷えと疲労に注意:外感(風寒)や虚弱(肺気虚)を予防
■ 肺を潤す薬膳素材(例)
- 梨(生津潤肺)
- 百合根(潤肺止咳)
- 白きくらげ(養陰潤肺)
- はちみつ(潤肺止咳、緩和作用)
- 麦門冬(薬膳茶やスープに応用可)
■ 肺の経絡を整えるツボ刺激
- 尺沢(しゃくたく): 肺の熱を清め、咳や痰を鎮める
- 太淵(たいえん): 肺の元気を補う、慢性咳嗽に
- 列欠(れっけつ): 肺経の要穴。風邪の初期や喉の痛みに
■ 季節別の肺ケアポイント
- 秋:乾燥による肺陰損傷を防ぐ(潤肺食材・湿度管理)
- 冬:冷えによる風寒咳嗽を予防(首・背中の保温)
- 春:花粉症や気温変化に備えた免疫強化(肺気補養)
⑨ まとめ|咳を“症状”ではなく“全身バランスのサイン”としてとらえる
中医学では、咳や喘息といった呼吸器の不調を、単なる「肺の問題」とは考えません。
「外邪の侵入」「気・血・津液の流れ」「臓腑の協調関係」—— それらすべてが乱れた結果として、咳や呼吸困難といった現象が現れます。
特に、慢性的な咳や息切れが続く場合、肺そのものよりも「脾・腎・肝」との関係や、「陰虚・痰湿・気虚」といった体質的背景を考慮することが必要です。
本記事では、咳嗽・哮病・喘証という中医学の基本分類に始まり、病因・病機・証型・治法・鑑別・現代疾患との対比・セルフケアまでを体系的に解説いたしました。
西洋医学とは異なるアプローチで、自身の身体の声を聴き、体質にあった養生や学びを深めていくことは、未病の防止や慢性疾患への理解にもつながります。
咳が続いてつらいとき、「肺が弱っているのかもしれない」と思うだけでなく、身体全体のバランスを見直す視点を持つことで、より根本的なケアが可能になります。
それが、中医内科学の知恵なのです。
この記事の分類
- シリーズ分類:プロ向け上級シリーズ