当帰芍薬散 vs 桂枝茯苓丸|月経トラブルに使われる代表方剤の違い
当帰芍薬散 vs 桂枝茯苓丸|月経トラブルに使われる代表方剤の違い 月経痛・むくみ・冷え・生理不順…。 女性にとって月経周期にまつわる不調は、とても身近で、しかし個人差が大きい悩みの一つです。 漢方では、同じ「月経トラブル」でもその背景にある体質や症状の現れ方によって、選ばれる処方が異なります。 本記事では、特に処方頻度の高い二大方剤―― 当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)と桂枝茯苓丸(けいしぶく […]
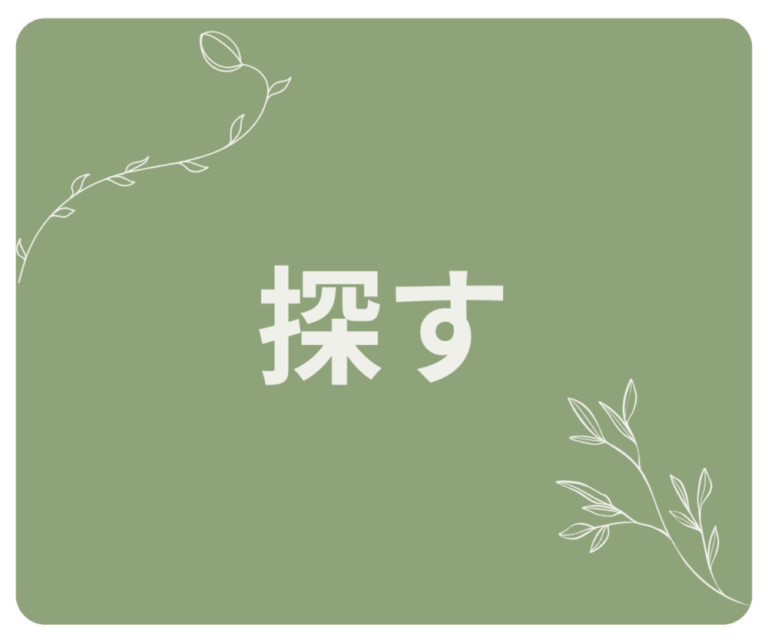
「冷え性」「不眠」「便秘」など、気になる症状から自分に合った漢方・薬膳・養生法を探せるカテゴリです。体質別や季節別の使い分けも学べます。
当帰芍薬散 vs 桂枝茯苓丸|月経トラブルに使われる代表方剤の違い 月経痛・むくみ・冷え・生理不順…。 女性にとって月経周期にまつわる不調は、とても身近で、しかし個人差が大きい悩みの一つです。 漢方では、同じ「月経トラブル」でもその背景にある体質や症状の現れ方によって、選ばれる処方が異なります。 本記事では、特に処方頻度の高い二大方剤―― 当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)と桂枝茯苓丸(けいしぶく […]
大黄甘草湯 vs 麻子仁丸|便秘のタイプ別で使い分ける漢方処方 便秘とひとことで言っても、その原因や体質によって適した漢方処方は異なります。この記事では、古くから多くの臨床例をもつ「大黄甘草湯(だいおうかんぞうとう)」と「麻子仁丸(ましにんがん)」を比較し、便秘のタイプ別に使い分けるポイントを詳しく解説します。 便秘にもタイプがある?|中医学の視点 中医学では、便秘は単なる「出ない」状態ではなく、 […]
補剤3兄弟を比較!補中益気湯・十全大補湯・六君子湯の違いとは? 「なんとなく全部“元気を補う”漢方だけど、どれを選べばいいの?」 そんな疑問を感じたことはありませんか? 中医学における補剤は、体力の低下や慢性疲労、消化機能の衰えなど、現代人の不調に多く使われる定番処方です。今回はその中でもよく処方される、補中益気湯・十全大補湯・六君子湯を比較し、それぞれの使いどころ・証の違い・構成の工夫を中医学の […]
疲れ・だるさの東洋医学的アプローチ 「休んでも疲れが取れない」「朝から体が重い」——そんな不調、感じていませんか? 現代人の多くが悩む慢性的な“疲れ”や“だるさ”は、西洋医学では原因が不明とされることもありますが、東洋医学(中医学)では明確な原因と改善法が存在します。本記事では、薬剤師 × 国際中医師の視点から、東洋医学的な疲労のタイプと、その解決アプローチについてわかりやすく解説いたします。 東 […]
冷え性に使える漢方3選|体の芯から温める東洋医学の知恵 手足が冷える、布団に入っても足が温まらない──そんなお悩みを抱える女性は少なくありません。特に冬場はもちろんのこと、夏のクーラーによっても冷えが深刻化するケースも。この記事では、薬剤師・国際中医師の視点から、冷え性に用いられる代表的な漢方処方を3つご紹介します。体質ごとに合う薬も異なりますので、ご自身の状態に合わせた選択の参考にしていただけれ […]
ストレスによる胃の不調が改善した薬膳例|心と脾にアプローチする中医学の知恵 「なんとなく胃が重い」「食べた後に気持ち悪くなる」「病院では異常なしと言われた」——そんな経験はありませんか? 実はこのような不調の背景に、“ストレス”が大きく関係しているケースは少なくありません。 今回は、ストレス性の胃の不調を抱えていた30代男性の症例をもとに、中医学的アプローチと薬膳の実践例をご紹介します。 🧍♂️ […]
アトピー性皮膚炎と食事改善での変化|中医学の視点から見た症例アプローチ 現代社会では、食生活の欧米化やストレスの増加により、アトピー性皮膚炎に悩む方が増えています。中でも「ステロイドはなるべく使いたくない」「体の内側から整えたい」というニーズから、漢方や薬膳に関心を持つ方も多く見受けられます。 今回は、実際に私が関わった20代女性のアトピー性皮膚炎に対する食事改善と漢方アプローチの症例をご紹介しま […]
60代男性/高血圧と不眠の併存に対する漢方アプローチ 「夜中に何度も目が覚める」「眠れないまま朝を迎える」──その一方で血圧は高め。 西洋医学的には「睡眠障害と高血圧の合併」として治療されることが多いですが、中医学では心と腎のアンバランスが一因と考えられています。 今回は、60代男性の実際の症例を元に、漢方的な視点から「高血圧+不眠」にどうアプローチするかをご紹介します。 症例紹介:60代男性の主 […]