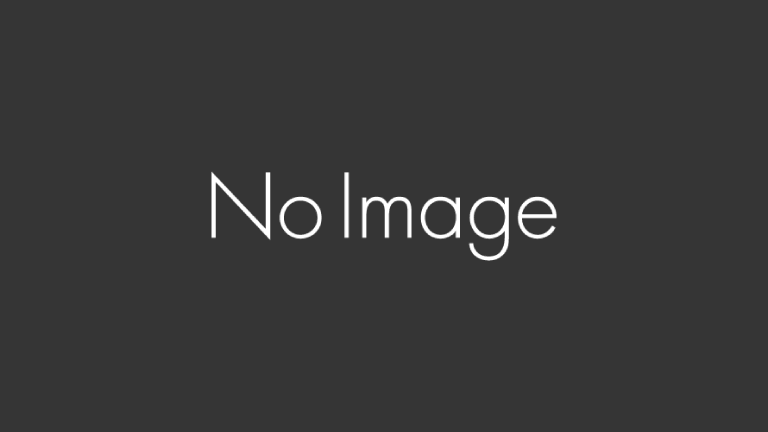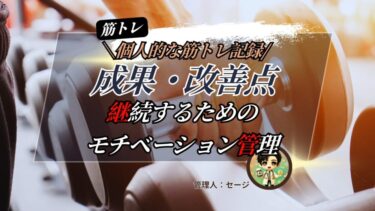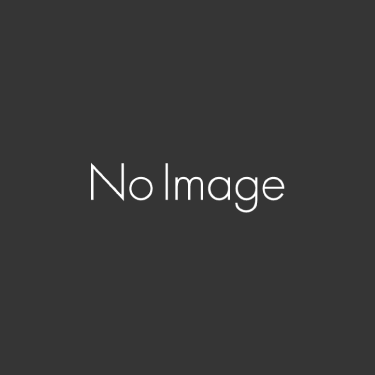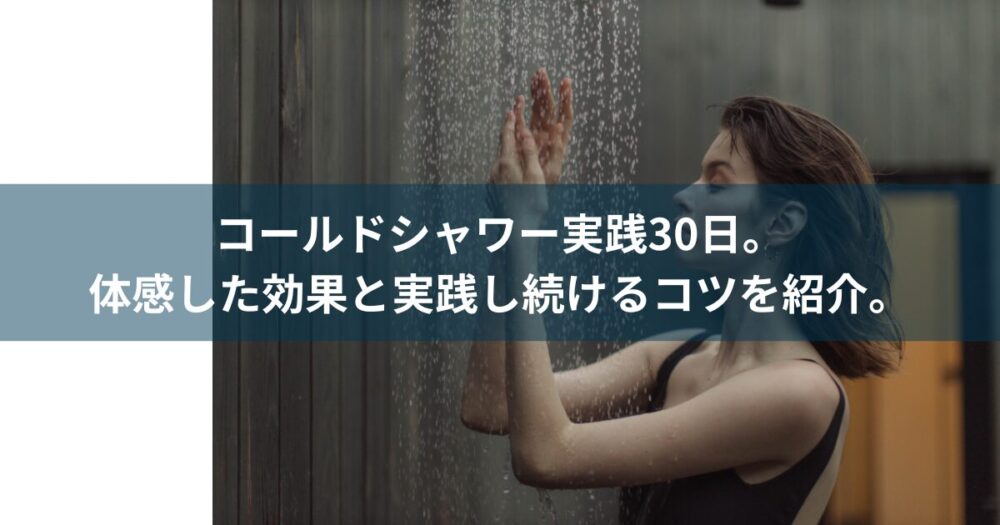糖尿病療養指導士の要点まとめ
- 1 療養指導士の役割と活動
- 2 インスリンとは
- 3 糖尿病の診断
- 4 糖尿病の基礎
- 5 糖尿病の検査
- 6 SMBG、CGM、isCGM
- 7 食事療法
- 8 運動療法
- 9 運動療法の指導
- 10 薬物療法
- 11 糖尿病の急性合併症
- 12 ライフステージ別支援
- 13 スティグマ、アドボカシー活動
- 14 高齢者の糖尿病(65歳以上のDM)
- 15 ケアの種類
- 16 災害時の対策
- 17 医療安全上の注意点
- 18 糖尿病患者の心理
- 19 DMのセルフケア行動
- 20 糖尿病患者の教育
療養指導士の役割と活動
糖尿病療養指導士の役割
- 自己研鑽し医療の進化に対応する。
- 新しい知識、技術を身にみつける。
- 治療チームぜんたいのLvアップ。
- 地域的なネットワーク構築。
- EBMの蓄積など治療へ貢献。
- 社会的認知の確立
- CDEJと地域CDEの役割分担
インスリンとは
膵臓ランゲルハンス島β細胞(膵ラβ)から分泌されるホルモン。
- 血中のグルコース(Glu)を細胞内に取り込んでエネルギー源として利用する。
- グリコーゲンや中性脂肪を合成する。
・慢性的にグルコースが利用されなくなる(糖代謝障害)
・血中にグルコースがのこるので高血糖になる。
では、高血糖が続くとどうなるのか。
・尿中に糖が排泄される(尿糖+)
・尿糖は、尿中の水分とNa排泄を促進させる(多尿・脱水)
・細胞内へグルコースが利用されないので、脂質やタンパク質からエネルギーを取るようになる(体重減少)
・脱水&体重減少でつかれやすくなる(易疲労)
・高血糖高浸透圧(HHS)やケトアシドーシスリスク高まる。
糖尿病の合併症一覧
・糖尿病性昏睡
・細小血管障害(神経障害、網膜症、腎症)
・大血管障害(足動脈の閉塞、壊疽、脳卒中、虚血性心疾患)
・その他(白内障、ガン、歯周病、NASH、皮膚病変など
糖尿病の診断
慢性的な高血糖を確認。
以下のどれかのパターンで糖尿病が確定する。
- 糖尿病型を2回確認。※1回は必ず血糖値でカクニン!
- 血糖値で1回糖尿病型+慢性高血糖症状(+)
- 糖尿病網膜症がある。
糖代謝異常の判断区分と診断基準
大前提として、「〇〇型」を示すだけであって糖尿病の確定診断ではない。
糖尿病型
以下4つのうち、いずれか一つ(Not全て)
- 早朝空腹時血糖126mg/dL以上
- 75gOGTT2時間180mg/dL以上
- 随時血糖値200mg/dL以上
- HbA1c6.5%以上
境界型
糖尿病型でも正常型にも属さないケース
正常型
以下の範囲内なら正常型
- 早朝空腹時血糖110mg/dL未満
- 75gOGTT2時間140mg/dL未満
※①が110-126mg/dLの間は正常高値と言われる。
糖尿病の基礎
インスリン作用不足の程度に応じて分類する
| 病態 | インスリン依存状態 | インスリン非依存状態 |
| インスリン | 絶対的に不足 | 相対的に不足 |
| インスリンの必要性 | 治療に不可欠 | 必要な場合もある |
| 血糖値 | 高い、不安定 | 比較的安定 |
| ケトン体 | 未治療:著名に高い | 増加することもあるが軽度 |
| インスリン分泌能 (空腹時Cペプチド) |
0.6ng/mL未満 | 1.0ng/mL以上 |
成因による分類は4つ
- 1型、2型
- 妊娠糖尿病
- 遺伝子異常
- 膵β細胞の遺伝子異常
- インスリン作用伝達の遺伝子異常
- その他
- 膵外分泌不全
- 内分泌疾患
- 肝疾患
- 薬剤や化学物質
- 感染症
- 免疫機序の稀病態
1型糖尿病の種類
- β細胞の破壊
- 絶対的なインスリン不足で起こる
- 急性発症
- 劇症
- 緩徐進行
| 急性発症 | 劇症 | 緩徐進行(SPIDDM) | |
| 特徴 | 膵ラ島自己抗体(+) 内因性インスリン分泌が枯渇 近年免疫チェックP阻害薬のSEとして注目されてる |
初診時 血糖値288mg/dL以上かつHbA1c:8.7%未満 発症時 尿中Cペプチド10μg/dL以上or血中Cペプチド0.3ng/mL未満 かつ グルカゴン負荷(食後2hr)血中Cペプチド0.5ng/mL未満(※インスリン分泌不全かどうかをみている) ※劇症なので1,2M以内の血糖値推移をみるHbA1cはそこまで高くならない。 |
経過の何処かの時点で、グルタミン酸脱炭素(GAD)抗体(+) もしくは 膵ラ島細胞抗体(ICA)が(+) |
| ケトーシス、ケトアシドーシス | 3M以内 | 1w前後以内 | 基本なし |
2型糖尿病
インスリン分泌低下、インスリン抵抗性大、過食、高脂肪食運動不足などでインスリン作用不足で発症。
インスリン非依存状態の糖尿病が90%以上を占める。
成人期以降に発症することが多い。
肥満や肥満既往歴がある症例が多い。
糖尿病の家族歴を有することが多い。
「遺伝子異常」指摘の糖尿病
膵ラβ機能に関する遺伝子異常
家族性若年糖尿病
ミトコンドリア遺伝子異常の糖尿病
新生児糖尿病
インスリン作用機構に関する遺伝子異常
インスリン受容体異常症A型
妖精症
その他の要因で発症する糖尿病
膵臓疾患で発症
・いずれも機能低下→インスリン分泌低下やインスリン抵抗性が生じて糖尿病へ至る。
・膵炎、膵切除、膵腫瘍、ヘモクロマトーシス(鉄代謝異常によって体内の鉄が過剰に蓄積し、臓器障害を引き起こす病気)など
カウンターホルモンの過剰分泌で耐糖能が悪化し発症
| 病名 | カウンターホルモン |
| 末端巨大症 | 成長ホルモン |
| クッシング症候群 | コルチゾール |
| 褐色細胞腫 | カテコラミン |
| 甲状腺機能亢進症 | 甲状腺ホルモン |
| グルカゴノーマ | グルカゴン |
| アルドステロン症 | アルドステロン |
| 膵ソマトスタチノーマ | 膵臓内外分泌機能抑制ホルモン |
肝疾患
慢性肝炎、肝硬変を伴い糖尿病(食後高血糖が著明)
糖尿病の検査
検査することの意義は以下の3点。
- 早期発見、早期診断のため
- 発症後の血糖コントロールの評価のため
- 合併症の早期発見、進行度評価のため
早期発見や診断のための検査項目
- 血糖値
- HbA1c
- 75gOGTT
- IRI(血中インスリン)
- インスリン分泌指数
- 血中&尿中CPR(Cペプチド)
- HOMA-IR(インスリン抵抗性指数)
- 自己抗体
血糖値【早期発見診断】
10時間以上絶食した後
早朝に
空腹のまま採血した
静脈血におけるブドウ糖濃度
HbA1c:4.6-6.2%【早期発見診断】
・約120日(1-2ヶ月)は、はなれない。
・故に過去1-2Mの平均血糖を反映する。
・全Hbに対する割合で表現される。
75gOGTT(経口ブドウ糖負荷試験)【早期発見診断】
・食後のブドウ糖の流れを再現する目的。
・食後高血糖を捉えることが可能となる。
・軽度の糖代謝異常も検出できる。
・ゴロは75g飲むなんてツーれぇ(200)…検査手順
・空腹状態の採血後に75gブドウ糖飲む。
・負荷後30min、60min、120minに採血。
・診断では120minを使う。※検査時の注意点
・検査前の3日間は炭水化物150g以上摂取してもらい
・検査前10-14時間は絶食
・早朝空腹時に実施
・検査終了までは水以外摂取禁止
・喫煙、運動も控える
IRI(血中インスリン)【早期発見診断】
・ブドウ糖はインスリンにより筋肉で消費され、余分は肝臓や脂肪細胞に貯蔵される。参考基準範囲
2.19-9.89μU/mL
ゴロ:に~く
※早朝空腹時IRIが15μU/mL以上ならインスリン抵抗性の疑い
でてるのにですぎている
Cペプチド【早期発見診断】
インスリン分泌時の副産物
プロインスリン→インスリン+Cペプチド(1:1の関係で出てくる)
参考基準範囲
空腹時血中:0.6-1.8ng/mL
24hr蓄尿:20.1-155μg/day
・ほぼ代謝されない。
・尿中にそのまま放出される
・1:1の関係なので間接的にインスリン分泌量を推察可能
・24時間蓄尿すれば1日のインスリン分泌量がわかる
・日の変動が大きいので3日は継続測定が望ましい
参考基準以下なら、インスリン出てないので、インスリン依存状態となる。
・血中CPR:0.5ng/mL以下
・尿中CPR:20μg/day以下
インスリン分泌指数とCペプチドの違い
いずれも、インスリンが出ているかどうかをみている。
違いは、
Cペプチドは副産物なのでインスリン量をシンプルに血中と尿中からみている。
対してインスリン分泌指数は
インスリンの基礎分泌や追加分泌の割合や
空腹時血糖値とインスリン値なども考慮している。
HOMA-IR(インスリン抵抗性指数)【早期発見診断】
インスリン治療している患者には実施しない。
抵抗性をみるだけ。
抵抗性:2.5以上
自己抗体【早期発見診断】
1型糖尿病の症例で発症初期に自己抗体が証明されている。(判定時期は抗体ごとに異なるし証明されないケースもある)
| 抗体 | 解説 |
| GAD抗体 | 抗グルタミン酸脱炭素酵素65抗体 |
| ICA | 膵島細胞抗体 |
| IAA | インスリン自己抗体 |
| IA-2抗体 | インスリノーマ関連タンパクIA-2抗体 |
| ZnT8抗体 | 陽イオン輸出輸送体抗体 |
発症後の血糖コントロールの評価
以下の指標で評価していく。
- 血糖値&HbA1c
- GA(グリコアルブミン)
- 1.5-AG(1.5アンヒドログルシトール)
- 尿糖
血糖値&HbA1c【発症後】
| 目標 | 血糖正常化 | 合併症予防 | 治療強化困難 |
| HbA1c | 6.0未満 | 7.0未満 | 8.0未満 |
※
治療目標は「年齢、罹患期間、低血糖のリスク、サポート体制」など考慮し、個別に設定する。(画一的はNG)
成人に対しての目標値であり、妊婦は除いている。(妊婦は別な段落で解説)
では、高齢者はどうか。
高齢者Ver
| カテゴリ1 | カテゴリ2 | カテゴリ3 | |
| 認知機能 | 正常 | 軽度 | 中等度以上 |
| ADL | 自立 | 基本自立 手段的に低下 |
基本低下 併存疾患機能障害あり |
| 薬物療法 SE:重度低血糖リスクなし |
HbA1c:7.0未満 | HbA1c:7.0未満 | HbA1c:8.0未満 |
| 薬物療法 SE:重度低血糖リスクあり |
65-75歳 HbA1c:6.5-7.5未満75歳以上 HbA1c:7.0-8.0未満 |
HbA1c7.0-8.0未満 | HbA1c:7.5-8.0未満 |
・カテゴリ別が認知機能とADL評価しているのが特徴。
・重度低血糖リスクありの場合、HbA1cに下限値が設定されているのが特徴。
GA(グリコアルブミン)【発症後】
GA=血中Alb+ブドウ糖 非酵素的結合
基準値:11-16%
ゴロ:いいいろだGAね
- 過去2-3wの平均血糖値を反映
- 低血糖、高血糖繰り返す人や薬物療法開始の評価ができる
- HbA1cの誤差でやすい妊婦、透析患者の評価ができる
- ネフローゼ症候群では低値になる
1.5-AG(アンヒドログルシトール)【発症後】
食事から摂取→ほぼ腎臓で再吸収される。
基準値:14μg/mL以上
ゴロ:いちごあんぐり、すてられる↓
- 血糖値が上昇→尿中排泄→即低下する
- 血糖値が正常化→捨てられず再吸収で緩徐に上昇
- 過去7-11日の血糖値を反映。
- 食事や運動に左右されない。
※SGLT2Iとα-GIでは平均値血糖値と比べ異常低値となるので注意。
尿糖【発症後】
- 血糖値が正常=尿糖も正常:陰性
- 腎臓には、排泄閾値があり、こえると出る。
- 閾値の血糖値:160-180mg/dL以上
その場合は、血糖値が低くても尿糖陽性となる。
反対に、血糖値が高くても尿糖が陰性になることもある。つまり、尿糖の有無だけでは糖尿病の診断はできない!
合併症の早期発見、進行度評価
合併症そのものの解説は別な段落で解説する。ここでは検査をまとめた。
末梢神経伝導速度【DM神経障害】
・DMでは、両側性障害となる。
・左右差がある場合整形外科的な神経障害を疑う。
・まず感覚神経から障害される。
呼吸心拍変動係数(CVR-R)【DM神経障害】
・心電図の波形R-R間隔を用いる→変動係数CVを求める
・自律神経がにぶくなると心拍数は変動しにくくなる。
※不整脈が頻繁にあると正確なそくていは不可能。
蛍光眼底、視力、細隙灯検査【DM網膜症】
検査にてDM網膜症があれば、糖尿病が確定診断となる。
尿中微量Alb【DM腎症】
腎機能低下→尿中Alb排泄
ACR基準値:30mg/gCr未満
↓超えると出てくる
微量Alb尿:30-299mg/gCr
顕性Alb尿:300mg/gCr以上
・尿タンパク陽性の前に、腎機能を評価できる
・随時尿で、ACR(Alb/クレアチン比)で評価する。
※日を変えてACRを測定。3回中2回位上、微量Alb尿でれば「早期腎症」となる。
eGFR(糸球体濾過量)【DM腎症】
血清クレアチニン用いるパターンと血清シスタチンCのパターンの換算式がある。18歳以上に適用。筋肉量、食事、運動の影響を受ける。
心血管疾患合併の検査一覧
・心電図(安静時、運動負荷試験、ホルター心電図)
・心臓超音波検査
・冠動脈CT検査
・心臓カテーテル検査
脳血管疾患合併の検査一覧
・頸動脈超音波検査
・CT
・MRI
ABI検査【末梢動脈疾患(PAD)】
足関節血圧/上腕血圧の比をみる。
ABI:0.9以下 下肢閉塞性動脈硬化症の可能性大!
・下肢動脈の詰まり、狭窄の有無を評価する
・通常足関節の方が高い(ABI高い)
・足が詰まると上腕が相対的に高くなる。
PWV(脈伝播速度)【末梢動脈疾患(PAD)】
心臓から押し出された血液から生じる拍動(脈波)速度を測定。
血管(動脈)硬い→脈波速い
加齢で上昇。
年齢不相応に高値:動脈硬化進行の疑い。
俗に言う血管年齢とかいうやつですね。
血中の脂質の値【末梢動脈疾患(PAD)】
男性:40-234mg/dL
女性:30-117mg/dLLDL-C:65-163mg/dLHDL-C:
男性:38-90mg/dL
女性:48-103mg/dL
SMBG、CGM、isCGM
ここでは血糖測定器について試験要点をまとめた。
食事療法
目的は2つ。
1,糖尿病患者が、健常者と同様の日常生活を営むのに必要な栄養素を接種する。
2,糖尿病の代謝異常を是正し、合併症の発症と進展を抑制する。
適正なエネルギー量を摂取する。良好な代謝を維持する。目標体重を保ちながら日常生活を送るようにする。
栄養素のバランスに気を配る。
エネルギー産生栄養素(炭水化物、タンパク質、脂質)の比率を適正に保つ。
そして、動物性脂肪や食塩の過剰摂取に注意することで、合併症の発症と進展を抑制することができる。
ビタミンやミネラルは代謝を円滑にする。
植物繊維は食後血糖の上昇を抑制する作用がある。
規則正しい生活は高血糖や低血糖を是正する。
1日の指示エネルギー量を3食に均等に分割、食事時間も一定の間隔にすることで食後血糖の変動を抑制する。
盛り付けは大皿盛りじゃなく、個別に盛り付け→食べ過ぎ防ぐ。
骨や殻付きの食材を使用するとボリューム増すし、満足感も得られる。早食いも防止する。
食べ方は食物繊維を先に食すことで高血糖を是正する事ができる。
よく噛むことで味覚の回復、満足感、食事量の減少、内脂肪に特異的な脂肪分解が期待できる。
エネルギー摂取量の目安
| 身体活動量 | 標準体重E量(/kg) |
| 軽い | 25~30 |
| 普通 | 30~35 |
| 重い | 35~ |
・高齢者のフレイル予防:大きい係数を設定。
・肥満で減量:小さい係数を設定。まず3%体重減らす。
・あくまで目安、乖離しすぎなら柔軟に変更。
・年齢、病態、身体活動量などによって異なる。個別化を図る。
マクロ栄養素PFCバランス
| マクロ栄養素 | 総摂取Eあたり |
| 炭水化物 | 40~60% |
| たんぱく | ~20%まで。 |
| 脂質 | 20~30% |
・高齢者においてはフレイル発症も考慮して少なくとも1.0g/kg/日以上とする。
・腎機能低下例では、タンパク制限ある場合あり。
・飽和脂肪酸は7%以下
・動脈硬化性疾患がある場合は、n-3系多価不飽和脂肪酸の摂取を増やす。
・トランス脂肪酸の摂取を控える。
ミクロ栄養素
食物繊維は食後血糖値上昇を抑制する。血清Choの増加防ぐ。便通も改善する。
動脈硬化性疾患ある場合は、25g/日以上を目標とする。
食塩相当量
18歳以上:男7.5g/d未満、女6.5g/d未満
心血管疾患抑制、高血圧合併、顕性腎症期移行6g/d未満
食品交換表
カーボカウント
カーボカウントとは血糖のコントロールに着目した食事療法。
※炭水化物のみを制限する糖質制限とは異なる。
基礎カーボカウント
・毎食の糖質量をできるだけ一定にする→乱高下是正。
・食後血糖の安定化をはかる。
・適しているタイプ:食事時間不規則。血糖変動でかい。食事の自由度を得たい。
応用カーボカウント
・接種する糖質量を食全員測定→血糖の値から都度インスリン投与量を決定し食後血糖を安定化させる。
・適しているタイプ:強化インスリン療法治療中の方
※肥満を伴う場合は、エネルギー調整を行ったうえで実施する。じゃないとやせない。
食習慣の調査と評価
患者の食習慣や具体的な食事内容を把握することで評価したい。
方法:食事記録法、陰膳法、24時間思い出し法、食物摂取頻度法、食事歴法など
内容評価と指導
調査した食事内容より、食品交換表や食品成分表などの媒体を用いて推定摂取量を求め、
指示量に見合った内容であるかを評価する。
また、栄養バランスが適正化を評価する。
過不足があれば指導をしていく。
間食、補食、外食、中食について
間食について
・間食は基本しない。
・する場合は、果物や牛乳を1日の指示範囲内でとる。
・食後血糖が長時間上昇する場合は控える。
補食について
・低血糖対策として必要なEを1日の指示EにプラスしてOK。
・運動前の補食は、吸収が遅い牛乳、卵、チーズ、クッキーなどを用いる。
・運動途中で低血糖の場合は、吸収が早い砂糖、ブドウ糖、ジュースで補う。
外食・中食について
・Eに過剰になりやすい。
・調味料として砂糖、みりん、潮、醤油など多量に用い、濃厚な味がおおい。
・表1、表5の食事が多く、表6の野菜が少ない傾向にある。
・栄養バランスがよくない。
・日頃から食事量を測定する習慣をつけておき、見極めるチカラを養う。
・積極的に野菜、海藻、きのこ類を食べる。
アルコール、嗜好品・菓子について
アルコール
・摂取量は1日25gまでが目安。
・個々の飲酒習慣によって個別化を図る必要あり。
・肝疾患や合併症の場合は禁酒。
・飲酒が許可された場合、発泡酒に含有される炭水化物Eに注意。
・アルコールは肝臓の糖新生を抑制する。
・インスリンや経口血糖降下薬を使用中では低血糖を起こしやすい。
・アルコールは表1と交換できない。
・飲酒を伴うつまみの取り方は指導で対応。一律禁止ではない。
嗜好飲料・菓子
・コーヒー紅茶はカフェインが多い。中枢神経、精神機能の亢進に注意。
・胃潰瘍、心疾患を有する場合は過剰摂取に注意。
・コーヒー紅茶は、砂糖、ミルク、クリームを入れなかればEがないので飲んでもOK。
・清涼飲料水、菓子に用いるショ糖(砂糖)は消化吸収が早く血糖値が急速に上昇しやすい。
・また中性脂肪も増加されるのでDMには好ましくない。
・低カロリー、カロリーオフの表示(20kcal未満/100g,100ml)
・ゼロ、無、ノン、レスの表示(5kcal未満/100g,100ml)
・無糖の表示(0.5g未満/100g,100ml)
運動療法
運動療法の目的は、インスリン抵抗性を改善し血糖値の症状を抑制、DM進展防止をすること。
運動の効果
・ブドウ糖、脂肪酸の利用促進→血糖値、体重減少。
・インスリン抵抗性改善。
・加齢や運動不足による筋萎縮や骨粗鬆症の予防につながる。
・心肺機能、運動能力が向上、爽快感や日常生活のQOL向上につながる。
・高血糖や脂質異常症の改善にもつながる。
運動療法の進め方は、メディカルチェックを実施→種類、強度、時間、頻度を決める。
メディカルチェック
問診、身体所見、胸部X線、安静時心電図、
一般検査、検尿、肝臓、腎臓スクリーニング検査、
運動負荷検査(心拍、血圧、心電図、酸素摂取量、乳酸)、
合併症に関する検査、体力テスト(筋力、柔軟性、片足立ちテストなど)
運動強度とは
一般に中強度の有酸素運動が推奨される。
最大酸素摂取量(Vo2max)50%前後のもの、運動時の心拍数でその程度を測定判断する。
心配運動負荷試験で呼気ガス分析で算出される。
METs
安静時代謝の何倍相当かを示す。(中強度は3METs)
運動の消費E=METs✕体重✕運動時間
例
3METsの歩行を体重60kg、30分実施。
3✕60✕0.5時間=90kcal
状態別:運動療法の方法【禁止、制限した方がいいケース等】
・空腹時血糖250mg/dL以上
・尿ケトン体中等度以上陽性
・急性感染症
・糖尿病壊疽
・高度のDM神経障害
網膜症
※重量挙げ、バルサルバ型運動、頭位下げる運動は眼底血圧上昇となるので避ける。
※レジスタンス運動はNG
腎症
大血管障害【監視下で推奨】
※合併していたとしても絶対禁忌ではない。リハプログラムに従い監視下で運動できす。
ASO(下肢閉塞性動脈硬化症)合併例でも原則、運動推奨される。実施により運動能力、疼痛体制、QOL改善が期待できる。
・骨、関節疾患あり(専門医の意見を求める)
神経障害【運動突然死に注意】
自律神経障害合併例の場合は、運動中突然死のリスクがあるので原則運動禁止。
しびれなどの末梢神経障害を有するしょうれいでは、改善が期待できる軽症に限って許可する。
足病変に対してハイリスクの場合は、フットケアが必要。
高齢者【サルコペニア予防】
高強度では血圧上昇を伴い危険性が高い。強度中等度以下が望ましい。
散歩、軽いジョグ、ラジオ体操、自転車、水泳など全身を使った有酸素運動が望ましい。
高齢者は筋力低下があるので軽いレジスタンス運動(ダンベル、チューブ)も考慮する。
運動中の血圧測定
負荷の高い運動は、副作用や心血管イベントの発生からも高い運動を持続するのは好ましくない。
安全性の観点から避けるべき。特にハイリスク時間じゃは実際の運動中にも血圧測定すべき。
運動時間
糖質と脂肪酸のコスパのよい燃焼時間は20分以上の持続とされる。
20分未満でも回数を重ねて実施することで意味がでる。20分以上持続が必須ではない。
歩行では、1回15-30分を1日2回、1日運動量として1万歩が適当。
日常生活における運動量で稼ぐのがよい(階段利用、通勤時歩くなど)
運動頻度
有酸素は中強度で週に150分以上が良い。
可能なら毎日、少なくとも週3回以上、運動しない日が2日以上続かないようにするのが良い。
レジスタンス運動は、連続しない日程で週2-3日が推奨される。
禁忌でない限りレジスタンス+有酸素運動を行うのがよい。
運動療法の指導
薬物療法
経口薬
注射薬
インスリンが必要な人【絶対的適応】
- インスリン依存状態
- 重度の肝障害、腎障害
- 高血糖性の昏睡
- 重症感染症
- 重度の外傷、侵襲大の手術
- 糖尿病合併妊娠
インスリンが必要な人【相対的適応】
- 2型DM、著明な高血糖
- 空腹時血糖:250mg/dL以上
- 随時血糖:350mg/dL以上
- 血糖降下薬で良好血糖コントロールが得られない
- ステロイド薬で高血糖
- 糖毒性を解除したい
体重に影響を与える経口血糖降下薬
インスリン注入ポンプ(CSII、SAP)
CSII(シーエスアイアイ):インスリン注入ポンプのこと。
基礎インスリン(ベーサル)と追加インスリン(ボーラス)を組み合わせる。
適応:1型糖尿病で、インスリン頻回注射療法でも血糖コントロールが不十分な患者。
SAP療法
服薬指導
自己注射
糖尿病の急性合併症
低血糖症状
中枢神経系:頭痛、眼のかすみ、動作緩慢、集中力低下、意識障害、異常行動、経典、昏睡。
薬剤による低血糖増強
その他低血糖誘発因子
アルコール大量摂取
低血糖予防、再発予防
原因を患者と話し合い、その結果を踏まえて再発予防に取り組む。
患者には、ブドウ糖とIDカードを携帯してもらう。
家族、友人知人、教員など体家越冬時の処置を説明し協力を得る。
合併症の進行した患者や低血糖をなかなか自覚できない高齢者であっても血糖管理を行い対策を打つ。
自動車運転において重症低血糖は最大の危険事項であるが故、無自覚性低血糖は、道路交通法では
「運転免許をあたえないもの、もしくは保留することができるもの」に該当する。
高血糖緊急症
高血糖緊急症は以下の2つに大別される。
- 糖尿病ケトアシドーシス(DKA)
- 高血糖高浸透圧症候群(HHS)
原因:いずれもインスリン作用不足による代謝失調
DKAとHHSの違い
DKA
インスリン拮抗ホルモン上昇↑
→脂肪分解
→肝ケトン体合成亢進↑
→代謝性アシドーシスとなる。
HHS
高血糖の悪循環で重篤な脱水となる。
高血糖緊急症の検査所見
| 項目 | DKA | HHS |
| 血糖 | 300~1000 | 600~1500 |
| ケトン体 | 尿中(+)~(+++) 血清:3mM以上 |
尿中(ー)~(+) 血清:0.5~2mM |
| HCO3- | 10Eq/L以下 | 16Eq/L以上 |
| 浸透圧 | 正常~300 | 350以上 |
| HbA1c | 7.3未満 | 7.3~7.4 |
| Na | 正常~軽度低下 | 150< |
| Cl | 95未満 | 正常範囲 |
| K | 軽度上昇、治療後低下 | 軽度上長、治療後低下 |
| FFA | 高値 | ときに低値 |
| BUN/Cr | 高値 | 著名に高値 |
| 乳酸 | 約20%の症例で5mMより大 | しばしば5mMより大 血液pH低下に注意 |
| 鑑別を要する 疾患 |
急性胃腸障害、肝膵疾患 脳血管障害、低血糖 代謝性アシドーシス、急性呼吸障害 |
脳血管障害、低血糖 けいれんを伴う疾患 |
| 注意すべき合併症 | 脳浮腫、腎不全 低K血症、急性感染症 |
脳浮腫、脳梗塞、心筋梗塞 心不全、横紋筋融解症、腎不全 動静脈血栓、低血圧 |
症状の徴候
| 項目 | DKA | HHS |
| 病態 | インスリン依存 | インスリン非依存 |
| 発症前の既往・誘因 | インスリン注射の減量、中止 インスリン抵抗性増大 感染症、心身ストレス 清涼飲料水の多飲 |
|
| 発症年齢 | 若年層 | 高齢者 |
| 前駆症状 | 激しい口渇、多飲、多尿、体重減少 全身倦怠感、消化器症状 |
明確なものはなし 倦怠感、頭痛、消化器症状 |
| 身体所見 | 脱水、発汗、アセトン臭 クスマウル呼吸、血圧低下、頻脈 |
脱水、血圧低下、循環虚脱 けいれん、振戦 |
乳酸アシドーシス
- 重篤な組織や低灌流、低酸素血症
- 基礎疾患
- 薬物使用
- ミトコンドリア機能異常
などの原因で著しい代謝性アシドーシスをきたす。
稀だが一旦発症すると予後不良の疾患。
診断基準
動脈血pH7.3以下、血中乳酸値5~6mM(45~54mg/dl)以上
BG系と乳酸アシドーシス
BG系由来はミトコンドリアの代謝障害が原因と考えられている。
メトホルミンの投与では、内服、非内服での有意差はなし。
BG系の使用上の注意
肝腎心肺昨日が低下している場合は使用しない
ミトコンドリア機能異常患者にも使用しない
ヨード造影剤使用の前後2日間は用いるべきではない
大量飲酒時や感冒などによる脱水時にも注意
高齢者への投与も慎重に。
糖尿病の慢性合併症
3大合併症(細小血管障害)
- 網膜症
- 腎症
- 神経障害、壊疽
大血管障害
- 脳梗塞
- 心筋梗塞、狭心症
- 閉塞性動脈硬化症ASO、壊疽
糖尿病網膜症(細小血管障害)
DM罹患20年以上→有病率80%以上。
硝子体:内部出血すると硝子体出血
水晶体:内部が濁ると白内障
黄斑:血管閉塞、新生血管、出血が問題。
糖尿病網膜症のステージ分類
| ステージ | 所見 | 治療 | 検査間隔 |
| なし(NDR) | なし | 血糖・血圧の管理 | 12M |
| 単純網膜症(SDR) | 毛細血管瘤 点状・斑状出血 硬性白斑 |
血糖・血圧の管理 | 6M |
| 増殖前網膜症(PPDR) | 軟性白斑 網膜内最小血管異常 無灌流領域 |
アスピリン 光凝固(PC) |
2M |
| 増殖網膜症(PDR) | 新生血管 硝子体出血 網膜剥離 |
硝子体手術 | 1M |
| 増殖停止網膜症 | PCやオペで沈静化 | 血糖・血圧の管理 | 3~6M |
糖尿病網膜症の診断と検査、アセスメント
1,定期的な眼底検査をする。
・散瞳薬点眼→15~90分で散瞳。もとに戻るのは5~8時間かかる。
→車の運転は控えるよう指導。
・周辺から出血するが初期の段階では無自覚。故に、視力低下に至りやすい。
→自覚症状の有無にかかわらず専門医による眼底検査が必要となる。
2,蛍光眼底造影検査(FAG)
・最小血管異常の診断やPC施工範囲の決定に行う。施行後、尿流に黄色蛍光物質が排出される。
3,糖尿病連携手帳で情報記録と共有する。
糖尿病網膜症の治療光凝固法(PC)
局所網膜PC
レーザー光線で毛細血管瘤や無灌流領域を凝固
→網膜への液性成分の漏出を止める
→黄斑浮腫を軽減する
汎網膜PC
レーザー光線で広範囲な無灌流領域を凝固
→新生血管形成因子を減らす→消退
硝子体切除術
PDRの硝子体出血、網膜剥離、黄斑浮腫、血管新生緑内障に有効。
※全症例に効果的というわけではない。
糖尿病性腎症
ステージ別の臨床特徴
| ステージ | eGFR | 尿中Alb/Cr比(UACR) |
| 1期 | 30以上 | UACR 30未満 |
| 2期 | 30以上 | UACR 30~299 |
| 3期 | 30以上 | UACR 300以上 |
| 4期 | 30未満 | 問わない |
| 5期 | 透析療養中 腎移植後 |
透析療養中 腎移植後 |
ステージ別の治療方針
| ステージ | 治療 | エネルギー (kcal/kg/d) |
たんぱく (g/kg/d) |
塩分 | カリウム (g/d) |
| 1期 | 血糖管理 | 25-30 | 1-1.2 | 制限なし | 制限なし |
| 2期 | 厳格に血糖、血圧管理 | 25-30 | 1-1.2 | 制限なし | 制限なし |
| 3期 | 適切な血糖管理 厳格な降圧治療 たんぱく制限食 過激な運動はNG |
25-30 | 0.8-1 | 6g未満 | 制限なし |
| 4期 | 厳格な降圧治療 低たんぱく 運動制限 |
25-35 | 0.6-0.8 | 6g未満 | 1.5未満 |
| 5期 | 透析・腎移植 | HD:30-35 CAPD:30-35 |
HD:0.9-1 CADP:0.9-1 |
6g未満 計算 |
2未満 制限なし |
低たんぱく食の適応となるケース
- 腎症1~2期だが進行性に腎機能が低下
- 腎症3期
- 腎症4期
※高齢者、サルコペニア、フレイルのリスクある症例は注意が必要。
目標体重あたり0.8kg/dを下回らないようにする。
腎症4期の治療注意
腎機能低下に伴い、必要インスリン量は減少する→低血糖に注意。
以下の治療も考慮する。
腎性貧血治療(Epo、HIF-PHI)
りん吸収阻害
活性型VD
球形吸着痰
高K血症治療
DM患者の透析療法
以下3つをスコア化して導入検討する。
- 腎機能(血清クレアチニン)
- 臨床症状
- 日常生活障害度
ライフステージ別支援
乳幼児・小児期の特徴
小児糖尿病のインスリン治療の特徴
| 頻回注射(MDI) Multiple Daily Injections |
持続皮下注射(CSII) Continuous Subcutaneous Insulin Infusion |
|
| 投与方法 | ペン型 | ポンプ注入セット |
| インスリンの種類 | 超速効型+持効型 | 超速効型のみ |
| 注射回数 | 4回/1d | 1回/3d |
| 調整 | 難しい | 0.025単位/hr で可能 |
| コスト | 安い | 高い |
| 携帯 | ペンのみ | ペン+常時装着 |
小児2型糖DMへの薬物療法の年齢別使い分け
| 年齢 | 日本 | 欧米 |
| 15歳以上↑ | SGLT2I GLP1 DPP4I |
10歳以上で一部使用可能となる。 |
| 15歳未満↓ | インスリン BG系 SU剤 |
低血糖時の救急処置としてバクスミー
点鼻のグルカゴン製剤。
- 単回使用で1回つかいきり
- 空打ち不要
なお、室温保存可能学校などでの重症低血糖発作時に、教職員の使用が可能となった。
教職員が使用できる条件は次の通り。
以下、4つは医師法 (昭和23年法律第201号)違反とはならない。
① 当該児童等及びその保護者が、事前に医師から、次の点に関して書面で指示を受けていること。
・ 学校等においてやむを得ずグルカゴン点鼻粉末剤を使用する必要性が認められる児童等であること
・ グルカゴン点鼻粉末剤の使用の際の留意事項② 当該児童等及びその保護者が、学校等に対して、やむを得ない場合には当該児童等にグルカゴン点鼻粉末剤を使用することについて、具体的に依頼 ( 医師から受けたグルカゴン点鼻粉末剤の使用の際の留意事項に関する書面を渡して説明しておくこと等を含む。)していること。
③ 当該児童等を担当する教職員等が、次の点に留意してグルカゴン点鼻粉末剤を使用すること。
・ 当該児童等がやむを得ずグルカゴン点鼻粉末剤を使用することが認められる児童等本人であることを改めて確認すること
・ グルカゴン点鼻粉末剤の使用の際の留意事項に関する書面の記載事項を遵守すること④ 当該児童等の保護者又は教職員等は、グルカゴン点鼻粉末剤を使用した後、当該児童等を必ず医療機関で受診させること。
(令和6年1月22日の厚生労働省医政局医事課長通知 医政医発0122第3号より)
痙攣をともなうような重症低血糖をおこしやすい。
血糖値:身体的に未熟+食事運動量も一定ではないため変動が急激で不安定。
夜間の低血糖には十分な注意が必要。場合によっては捕食も与える必要がある。
本人が自ら親に低血糖状態を訴えることは非常に難しい。故に対応が遅れる危険性もある。
反面、乳幼児期に発症した子にとっては、注射・SMBG・低血糖対策が「当たり前」の生活になっている。
また、しつけが必要な時期とも重なるため、良好な食事と生活習慣を家族で整える良いタイミングでもある。
両親
子どもの糖尿病をある程度受容してあげる必要がある。
心理面的な安定した状態で育児や疾患管理にあたる必要がある。
母親は子どもが1型糖尿病を発症したことについて強い自責の念を持つことが多い。
このことから疾患管理に専心する傾向がある。それにより血糖値やHbA1cの推移に一喜一憂しやすい。
医療者側
母親に負担が集中しないような家族支援が必要となる。
両親の気持ちを受け止めたうえで子どもの生地全体や少し先のことを客観的視点思って助言する。
父親には母親の負担軽減に関する指導や教育計画をするのではなく、母親と同様に発症初期から指導教育を計画する。
乳幼児期の療養指導の特徴
低血糖症状を家族全員が理解しておくようにする。
グルカゴン注射の手技は、家族全員が習得しておくようにする。
18歳未満は1型DMも2型DMも小児慢性特定疾患を申請できる。
親が低血糖を心配するあまり、SMBGの頻回とならないようにする。
新生児・乳児期はHbA1cが当てにならないのでグリコアルブミンを用いる。
主治医・かかりつけ医・救急病院の連絡先を明記し外出の際は親が携帯する。
インスリンの作用時間、血糖値の評価を伝え危険の予測ができるよう指導する。
小児糖尿病サマーキャンプなどへの参加は自己管理習得の有効な機会の一つである。
日々の血糖値に一喜一憂せず、長期視点で治療効果を見据えて将来目標をもつよう指導する。
3歳頃からは「欲しくない時間に捕食をたべなけれならない矛盾」を自覚し始める。理解できるよう繰り返し説明する。
学童期
体育の授業は参加させる。(無理なときは休む)
注射・SMBG・捕食が安心して実施できる環境を整えてあげる。
体格、清月、年齢、生活活動強度に応じた適切な食事量を摂取する。
運動会などの運動量が多い日はインスリン量を調節する場合もある。
修学旅行では、緊急時に対応できる医療機関への紹介状を持参させる。
小学校高学年の指導目標:SMBG、注射の自己管理ができるようになること。
正常な成長発育に必要な栄養素とエネルギーをきちんと摂取させ制限はしない。
ただし肥満の場合は、標準体重に対するエネルギー必要量の90~95%に調整する。
成長ホルモンや性ホルモンの影響で血糖コントロールが不安定な時期でもある。
身体活動活動に関する生活習慣も一緒に合わせて改善していくよう指導を行う。
思春期は生活や活動が拡大が進む時期のため、周囲の介入が逆効果になりやすい。
個人として尊重し見守りつつ、待つといった関わり方をこころがけるようにする。
恋愛によって自己管理の目標が背一定され血糖コントロールに良い効果を与えることが多い。
この時期でも糖尿病サマーキャンプへの参加は、セルフケア習得の良い機会として活用できる。
中学校の指導目標:自分の病気を正しく理解し自己管理について周囲に説明できるようになること。
担任の変更時にはその都度家族から持病について話をする。必要に応じて医療者側からも説明を加える。
学校の献立は事前に確認し食べる量や食品交換の調製をする。弁当持参よりみんなと一緒に食べることを優先させる。
1型DMの場合は、発症時や入学時にDMの知識・治療・療養行動を医療者側から学校側に説明し教師全員の理解を得る。
病型
インスリン治療
MDI
CSⅡ
グルカゴン点鼻粉末剤(バクスミー)
就労期
糖尿病腎症3期からは、作業程度に配慮するのが一般的である。
糖尿病腎症4期からは、軽い勤務程度とするのが一般的である。
起立性低血圧がある場合は、高所作業等くれぐれも配慮すること。
現時点で日本において糖尿病患者を労働者としてその権利を守る法律はない。
勤務時間が不規則な職業であっても制限や条件が付けられていることはない。
血糖コントールが乱れやすい職業の場合は、自己管理を徹底する必要がある。
職場に自身が糖尿病であることを知らせるかどうかは患者自身の判断である。
職場によっては周囲の理解を得られれば比較的望ましい時間に食事摂取が可能。
重度糖尿病網膜症で失明しても生活訓練、職業訓練であんまマッサージ指圧師、鍼灸師などの資格が取れる。
療養就労両立支援指導料
妊娠期
生理的なインスリン抵抗性は
胎盤由来のホルモンや脂肪組織の炎症性変化で起こる
つまり、すべての妊婦にインスリン抵抗性が生じる。
妊娠中の糖代謝異常の分類
| 糖尿病合併妊娠 | 妊娠糖尿病 | 妊娠中の明らかな糖尿病 |
| 妊娠前からDM | 妊娠中にはじめて 発見、発症 DMに至らない糖代謝異常 |
妊娠糖尿病の基準より高く、DM基準を満たす |
| 空腹時血糖126mg/dL HbA1c:6.5% |
母体の高血糖が及ぼす影響
| 母体 | 胎児 | 出産後 |
| 流産、早産 血圧上昇 羊水過多 |
高血糖 先天奇形 体重増加 |
巨大児 新生児低血糖 黄疸 呼吸不全 糖尿病リスク大 肥満リスク大 |
糖代謝の特徴
インスリン抵抗性
母体の高血糖が及ぼす影響
妊娠前BMI25以上=肥満妊婦の場合、必ずしも付加量を加える必要はない。
ただし、体重減少する場合は極端な食事制限は避ける。
奇形、低体重児、低Ca血症などを起こしやすい。
胎児の奇形の有無は妊娠8週目までに決定する。
妊娠前BMI25未満=非肥満妊婦の妊娠初期では妊娠期に必要なエネルギー付加量は50kcalである。
食後高血糖や、食前低血糖、飢餓性ケトーシスを予防するために1日総エネルギー量を3回の食事と3〜4回の間食に分けた分食にする。
妊娠中の血糖コントロールに鉄剤は影響を及ぼさない。
妊娠中の糖代謝異常
妊娠糖尿病(GDM)
妊娠中に初めて発見または発症した糖尿病に至っていない糖代謝異常
スクリーニングは妊娠初期と妊娠24〜28週に随時血糖値を測定する。
最大インスリン需要量は1型DM合併妊娠では非妊娠時の約1.5倍、2型DM合併妊娠では約2.0倍。
血糖コントロール不良で起こりやすい状態:ケトーシス、糖尿病網膜症、糖尿病性腎症の増悪、流産早産、妊娠高血圧症候群、羊水過多症、尿路感染症などがある。
糖尿病合併妊娠
妊娠前から糖尿病が存在している妊婦の糖代謝異常
妊娠中の明らかな糖尿病
スクリーニングと診断基準と目標値
食事療法と薬物療法
子どもをつくる前からの教育ケア
スティグマ、アドボカシー活動
スティグマとは
差別、偏見からの烙印
糖尿病スティグマとは
「自己管理が悪いから糖尿病になった」というものが典型例
医療従事者は正しく認識し、いわれなき差別には不当であると社会に発信していく必要がある。
医療関係者が糖尿病患者のための思って発した言葉が反対にスティグマとなり傷つけてしまうことがある。
一般に医療従事者と患者は上下関係になりやすい。
関係構築が重要。また環境にも左右されるのでスティグマを感じさせない環境づくりが医療従事者の役割。
スティグマの類型
| 社会的スティグマ (社会規範からの逸脱) |
乖離的スティグマ (模範イメージから乖離) |
自己スティグマ (自尊心低下) |
|
| 経験的スティグマ (実体験) |
生命保険に加入拒否られた 住宅ローンを拒否られた 就職できなかった 寿命が短い |
間食を咎められた インスリンを拒否ると叱責うけた |
糖尿病という言葉のネガティブイメージ 治療成果に対し、事故を必要以上に卑下 |
| 予期的スティグマ (スティグマへの恐れ) |
糖尿病のことは誰にもいわない | しぶしぶ注射をしている 隠れて食べる |
宴会・会合にいけなくなる 誰にも相談しない |
アドボカシー
用語、支援するなどの意味を持つ。
糖尿病では、偏見やスティグマをなくし糖尿病のある人が自信を持って取り組めるよう支援すること。
スティグマのない糖尿病治療計画(心遣いと配慮を持って接する)
| 尊厳 | 眼の前の糖尿病のひとも医療機関を出てれば立派な社会人であることを忘れずに対応する。 |
| 傾聴 | 話を否定せずに傾聴する。 |
| 禁止 | 拒否否定を禁止、そのような言葉を用いない。 |
| 提案 | 指示、命令はしない。提案する。 |
| 深慮 | そうせざるを得ない理由があることを深慮する |
| 人生目標 | 治療のためだけに生きてはいないことを忘れずに対応する。 |
また、ケアが目指す方向性は
- ケアを受ける側は、決して社会的に孤立などしていないということ。
- 病気や身体症状があってもケアされる人は、高い自己尊重を維持しているいうこと。
- 家族、友人支援者との関係性が良好であるということ。
- ケアされる側が落ち込んだりせず、他者と交流できること。
| 活動レベル | DM患者 | 医療従事者 | 日本糖尿病協会 の支援事業 |
| 個人 | 学校・職場などへの働きかけ | 教育・支援体制の確立 眼科、歯科などとの連携 |
糖尿病手帳の提供 糖尿病教育支援ツール提供 |
| コミュニティ | DMキャンプ、市民公開講座等への参加 | DMキャンプ、市民公講座、DM重症化予防への参画 | DM未ャンプ、フェス、市民公開講座の開催 |
| 全国 | 日本糖尿病協会の活動へ参加 | 日本糖尿病協会、学会への参加活動、行政立法府に低減 | 世界糖尿病デー、糖尿病重症化予防 |
| 国際 | 国際学会等にて世界の状況をシェア | 国際学会にてアドボカシー活動を報告 | 国際糖尿病連合での活動 |
高齢者の糖尿病(65歳以上のDM)
高齢者の安価でも、75-80歳以上でADK,認知機能障害、腎機能低下、重症低血糖、脳卒中が起こりやすい。
注意すべき高齢者DMは、
・75歳以上
・ADL低下、認知機能障害ある65-74歳
高齢者糖尿病の頻度、成因、特徴
R01の統計によると、高齢者糖尿病のうち、70歳以上男性が26%、女性が20%を占める。
高齢者のサルコペニアは糖尿病の発症&増悪因子となる。
ほかに
加齢に伴う膵β細胞のインスリン分___泌低下
体脂肪量の増加、骨格筋量低下に夜インスリン抵抗性の増加
身体活動量低下
などがある。
- 口渇、多飲、多尿など高血糖症状がでにくい。
- 無自覚低血糖、非典型的な症状を呈する
- 重症低血糖をきたしやすい。
- 食後高血糖が著明な例が多い。
- 脱水、感染症を契機に高浸透圧高血糖状態になりやすい。
- 無症候も含め動脈硬化性疾患をきたしやすい。
- 加齢に伴う腎機能低下も加わり薬物有害事象が起きやすい。
- 社会的サポートの不足&経済状況問題により、介護保険などの社会サービスを必要とすることが多い。
合併症や併存疾患の特徴
- 糖尿病性細小血管障害、動脈硬化性疾患の合併頻度が高い。
- 脳卒中、虚血性疾患、心不全、糖尿病腎症をきたしやすい。
- 多疾患を罹患しやすい。
- 特に高血圧、脂質異常症、心不全、骨粗鬆症、変形性関節症、誤嚥など。
- 低血糖、高血糖、ポリファーマシーをきたしやすく予後が不良。
- 老年症候群を2倍きたしやすく、要介護、QOL低下、死亡リスクを高める。
高齢者に発症した糖尿病は、一般的には耐糖能障害や合併症の発症進展は軽度である。
高齢者糖尿病の合併症は、一般的に若年壮年と同じである。
慢性血管合併症には、糖尿病細小血管症と大血管症が含まれる。
高齢者糖尿病の昏睡は、HHSが多く、DKAは稀である。
認知機能OK+ ADL OK 重症低血糖症リスクなし Hb A1c7.0
認知機能OK+ ADL OK 重症低血糖症リスク有り
65〜75歳未満:Hb A1c7.5%未満
75歳以上:Hb A1c8.0%未満
厳格にしすぎて低血糖になるリスクを減らしている。
高次脳機能障害をきす症例がある。
定義
特徴と診療ポイント
個人差が大きい
治療が難しいケースも多い。
総合的な評価項目
ADL
フレイル
サルコペニア
認知機能
管理項目とその他留意点
検査項目が高齢者独自
カテゴリー1,2,3
9%以上では急性合併症感染症など死亡リスクが急増するので、8.5%以下
低血糖のリスク:認知症と心血管イベントリスクが上昇するため
食事療法の留意点
適正な総Eの摂取とバランスをとる食事は、高血糖、脂質異常症、肥満の是正に有効。
低栄養になりやすいので注意が必要。
目標体重を一律に定めない。年齢、臓器障害など患者の属性や代謝状況を評価しつつ、目安となる体重を段階的に再設定するなどじゅうなんに対応する。
食事摂取量やQOL維持に配慮した減塩の実践が推奨される。
重度の腎障害がなければ十分タンパク質を摂ることが、フレイルサルコペニアの予防につながる。
運動療法の留意点
| 有酸素運動 | レジスタンス運動 | バランス運動 | ストレッチ |
| 歩行、ジョグ 水泳 |
腹筋、水中歩行 ダンベル、腕立て スクワット |
片足立ち ステップ運動 体感バランス運動 |
大腿四頭筋 アキレス腱 腕肩周囲筋 |
薬物療法の留意点
社会的支援
介護のリスク
介護保険制度の活用
地域包括ケアシステム
ケアの種類
フットケア
なぜフットケアが必要なの?
- 神経障害が起きやすく早期発見が困難
- 結果、重症化しやすい。再発もしやすい
- 血糖改善しても大幅な回復が困難
- 足病変の患者は全心血管障害が進行してる事が多い
- 足壊疽や切断となるとQOL向上低下し、生命予後も不良
フットケアの目的ゴール
- 足病変予防と啓発をする
- 足の変化と身体の変化を結びつけて理解させる
- セルフケアへつなげていく
- ハイリスク患者へ定期的な観察・指導をする
ハイリスク患者とは?
- 足病変や切断の既往歴あり。
足の観察ポイント
予防的な項目
傷や異常をみつけたら
清潔保持と乾燥予防
爪の切り方
靴選びのポイント
やけどを未然に防ごう
下肢切断患者への指導
シックデイ
シックデイとは
合併しやすい感染症
尿路、呼吸、消化器、皮膚
対処:シックデイルールに従う
ルール内容
内服薬の対応
注射薬の対応
こんなときは即病院受診すべし
外傷や外科手術が必要なときはこんなとき
受診の際に必要な情報
改めて自己管理の重要性を理解させる。
旅行時
海外旅行
災害時の対策
原則
平常時すること
災害時すること
薬物療法
血糖変化への対処
避難生活の注意点
脱水予防
感染予防
足病変予防
妊婦への対応
心理面の支援
DiaMAT
パンデミック時
医療安全上の注意点
針刺し事故
インスリンの希釈・投与法
自動車の運転
放射線検査
糖尿病患者の心理
なぜ患者の心理が重要なのか
悲観のプロセス
悲観プロセスへの支援方法
DM発症と診断時の心理
DM療養中の心理
身体状況の変化と心理
治療変更時の心理
スティグマ
アドボカシー
DMのセルフケア行動
セルフケア行動を促す考え方
セルフ・エフィカシー
自己効力感の高める情報と方略
変化ステージモデル
前熟考
熟考
準備
実行
維持
完了
変化プロセスと定義
エンパワーメント
ストレスマネジメント
コンプライアンスとアドヒアランス
認知行動療法
患者心理と行動に配慮した支援
具体的な面接技法
家族の支援
変化と援助
糖尿病患者の教育
意義
DMガイドライン2019で教育の有効性ありとされた。QOL向上の一助になる。
ただし、その教育と支援は、行動心理学に裏付けされたもので行う必要がある。
患者自身が主体となる。
自分の生活習慣と価値観と折り合いをつけて治療行動をライフスタイルにいれる事ができるようにするのがゴール。
サポート目標の設定の仕方
・患者毎に身体的な課題を踏まえる。
・個々の背景と価値観を考慮する
・治療上必要なこと+患者が知りたいこと+なりたい願いを理解し設定する。
具体的な把握項目
・生活背景、生活習慣、病態、DMへの考え方・感情、性格。
・学習能力、過去の学習体験、家族の援助の有無
・阻害要因、中断理由や原因
サポート計画の作成とメンバー
医師、看護師、管理栄養士、薬剤師、臨床検査技師、理学療法士など関係する医療スタッフが集まって決める。
各医療スタッフの役割を明確にする。連携を図式化する。
必ず施設長に提出、病院全体の協力を依頼し得てやる。
治療方針は医師が作成。それに基づき各スタッフが個別にさらに作成する。
決定事項はメンバーと共有する。
薬物療法:医師薬剤師看護師
食事療法:医師管理栄養士看護師
運動療法:医師理学療法士健康運動指導士看護師
SMBG:医師臨床検査技師看護師薬剤師
メンタルケア:メディカルソーシャルワーカーも含める。
訪問診療:医師訪問看護師在宅介護支援関係者も含める。
地域支援:行政や医療関係者が健康教育、疾病予防教育、啓発活動などを企画している。
目標を3つの領域で設定する。教材も使う。
・知識面
・技能行動面
・態度価値観心理面
知識
・教科書、テキスト、資料
・視聴覚教材(ネット、教材ソフト、スライド、動画、ポスター)
・臓器模型、人体模型、フードモデル
・プレテスト、ポストテスト
技能
・食事療法
・運動療法
・薬物療法
・合併症
態度価値観心理面(動機づけ)
・患者中心のカウンセリング
・自己管理行動へのフィードバック
その他
・糖尿病カンバセーションマップ
動機づけが難しい理由
・そもそもが潜在的に無症状、無症候
・食事療法&運動療法のコンプ不良しがち
・コンプ不良でもすぐに悪化しない。徐々に蝕む。
・空腹感と疲労感を感じやすく、治療のせいだと誤認しがち
・勘違いしやすい
1、尿検査で陰性判定になりやすい
2、たまにOGTTが改善する
3、自覚症状が消えると完治
4、合併症の所見と代謝調製の指標が一致しない。
治療支援の原則
患者自身が能動的に学習するようにしていく
・エンパワーメント
・アンドラゴジー(成人教育)
・わかりやすさを重視
→学習者の達成能力の少し上を問いかける。
→既知から未知に進む
→単純なもの→徐々に複雑なもの
→学習者の認識の近いもの→遠いもの
学習者の課題をはっきり認識させる
我々CDEの役割は、信頼関係の構築がなにより重要
良きパートナーとして患者の立場になり、患者自身が気づき成長できるように支援する。
NG:否定的な判断をする、一方的な働きかけばかりする。先入観をもつ、途中で口を挟む、
GOODM:共感と傾聴。コーチング
PDCAサイクル&問題解決思考
P:アセスメントの視点項目
新滝的初見・管理状態
治療に関すること
合併症の有無と程度
ライフスタイル
患者のメンタル面
家族構成と社会活動
指導と評価
・患者に関する評価
DM治療目標の達成度で評価
- HbA1c:7%未満
- 血糖値:空腹時130mg/dL未満、食後2hr:180mg/dL未満
- 血圧:130/80mg
- 脂質:LDLC:120mg/dL未満、HDLC:40md/dL以上、TG:mg/dL未満
- 体重:個別に目標設定
合併症の程度を評価
予防行動を評価
心理面の評価
・DMを受け入れられているか
・DMの適切な知識があるか
・DMの恐怖や不安があるか
・DMによる制限されている思いがあるか
・DMへの肯定的な面を見いだせているか
社会面の評価
・家族の協力を得られているか
・治療行動に対する直接的な協力が得られているか
・精神的協力が得られているか
・職場学校地域コミュでの理解と協力がえらえているか
・医療従事者との関係は良好か
教育システムの評価
・効果
・計画
・資料
教育の形態
集団
糖尿病教室
小児糖尿病サマーキャンプ
グループ討論会
チーム医療